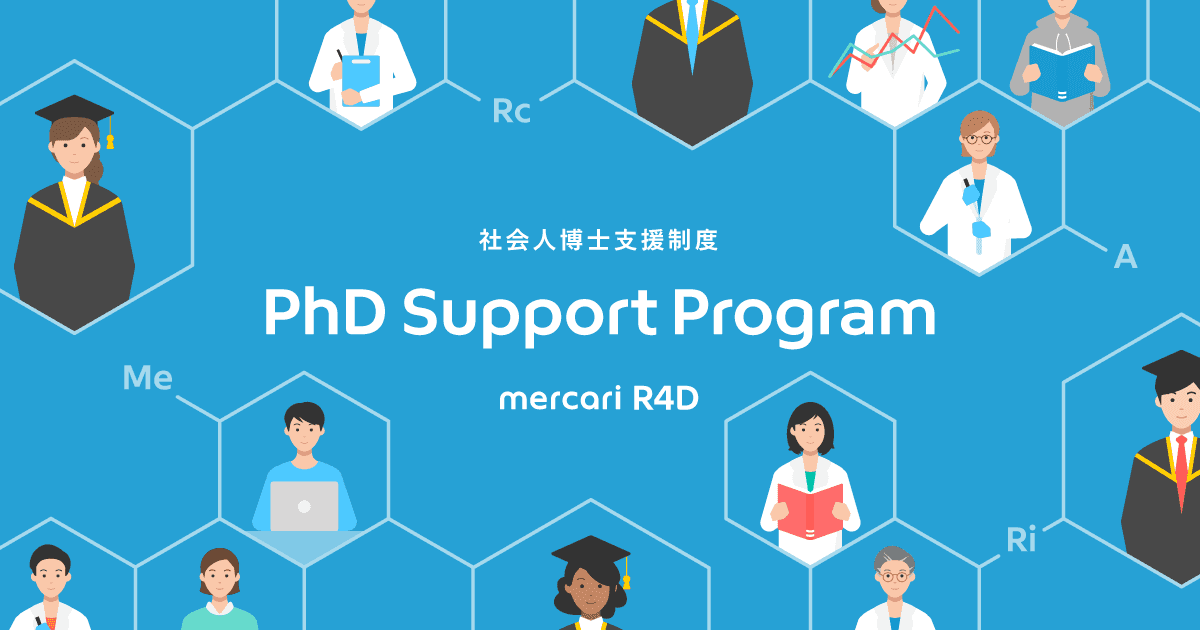こんにちは! R4DのResearch Acceleration Teamのnetchです。
mercari R4Dでは、メルカリ社員の博士号取得を促進するため「Mercari R4D PhD Support Program」という制度を運用しています。第5期メンバーを社内で募集するのに合わせて、社内で本制度に関するOpen Doorを開催しました。
このイベントでは、制度の詳しい内容の紹介だけでなく、過去に社会人として働きながら博士号を取得したメンバーの体験談を聞くパネルディスカッションを行いました。本記事では、その様子を紹介します。社会人博士についてご興味ある方の参考になれば幸いです。
Mercari R4D PhD Support Programについて
「Mercari R4D PhD Support Program」は、社員の研究活動を支援するために、2022年から導入された社会人博士課程支援制度です。
支援内容は、3つの柱を掲げています。1つ目は学費の全額負担です。年間上限200万円程度(入学金等を含む)の学費を原則3年間負担します。2つ目は研究時間支援制度です。業務時間を週0日、3日、4日 、5日から選択でき、研究と業務のバランスを個人でデザイン可能です。なお、給与は稼働時間に応じて支給されます。3つ目は、R4Dのサポートです。本プログラムはメルカリの研究開発チームである我々R4Dが運営しているので、R4Dが持つ学術界における知見や繋がりを活用し、研究内容や博士課程受け入れ先の相談、メルカリの取引データ等の機密情報の研究利用の手続き等のサポートが用意されています。
この制度の対象者は、メルカリ日本法人に所属するメンバー全員です。支援対象は日本国内の大学の博士課程で、研究領域は不問です。R4Dの研究領域に限らず、人文社会学系や学際系の研究でも応募可能です。
選考は書類選考から始まり、1次面接と最終面接を経て採用が決まります。
なお、選考を経て本制度に採用された後は、半年ごとの研究進捗報告と1年ごとの年次報告が求められます。研究相談や各種手続き相談、特許関連の相談などは随時R4Dがサポートしております。
※参考記事:2/11(火・祝)開催:北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)が主催する『「次世代リカレント研究・教育」シンポジウム』に登壇してきました
社会人博士の体験談
社会人博士と聞くと、「働きながら大学院に通うのはどんな感じだろう?」「やっぱり仕事と研究の両立は大変なのだろうか?」という疑問を抱くことと思います。というわけで、今回は実際に社会人として働きながら博士号を取得したkeinyさんとfujimiyuさんをお招きし、お二人の体験談を伺いました。
社会人として働きながら博士号を取得しようと思ったきっかけは?
keiny:自分の専門分野はデザイン方法論なのですが、専門性を証明するような資格はありません。そこで、博士号を取得することで自分の専門性を証明したいというのが最初のきっかけでした。博士号は海外の人にも通用するというメリットもあります。
fujimiyu:研究職に就きたい場合は博士号が必須だからです。ちなみに、当時の職場(国立国語研究所)で働く人たちが博士号を持つ人ばかりで、「博士号は取得するもの」という環境にいたことも理由の一つです。
博士号取得のメリットは?
keiny:特定の分野を深められるのはもちろんのこと、問いを立てて新たな解決策を導き、その解決策が妥当であることを評価するという汎用的な研究プロセスが身につくことです。
fujimiyu:1つ目のメリットは、自分のキャリアが説明しやすくなることです。「このテーマ・問題だったらfujimiyuさんに聞いてみよう」と声をかけてもらいやすくなります。2つ目は、「自分で研究をここまで達成できた」という納得感と自信を得られることです。他分野の研究をすることになっても、見通しが立つようにもなりました。
博士課程ではどんな日々を過ごしていた?
keiny:私の研究は「何かをデザインして、その結果を評価する」という性質上、思うような結果が出ないこともある不確実性の高いテーマだったのですが、それでも諦めずに頑張っていました。研究が思うように進まなかったり査読に落ちたりしてへこむこともありましたが、「この失敗の経験から学ぼう」という姿勢でいました。
この姿勢を続けるためには、自分の研究が面白いと思う知的好奇心が重要です。好奇心を維持するために、流行に流されすぎないこと、査読に通しやすいからという理由でテーマを選ばないことは意識していました。
fujimiyu:仕事をしながらの研究なので、やはり時間との勝負でした。私は「とにかく3年で博士号を取得する」と決めていたので、いつ調査して、いつ分析して、いつ論文を書き、いつ学会発表をするかについて綿密な計画を立てていました。特に学会の開催日は決まっているので、その日に合わせて研究を進めていました。また、博士号を取得するには査読付き論文を最低3本書かなければならなかったので、論文を提出する学会もあらかじめ決めていました。
仕事と研究の予定をパズルのように組み合わせながら進めていました。ただ、論文を書く際は執筆に集中したかったので、他の人の都合で決まる予定が入らないようにブロックして、まとまった時間を確保するようにしていました。当時は研究所の仕事と大学の非常勤講師を掛け持ちしていたのですが、研究所の仕事で忙しくなりそうな業務を事前に対応しておいたり、大学の授業が休みの時期を活用したりしていました。周りの人の協力も大事ですね。
「仕事する」と「研究する」をどのように両立していた?
keiny:研究では「何が本質か?」「なぜそれをするのか?」と考える一方で、仕事では現実的な解を出して実行することが求められるので、そのバランスを取るのが大事でした。仕事で本質を問いすぎて時間がかかりすぎたり、研究を現実的な実行案に落とし込もうとしすぎたりと、研究と仕事のモードの逆転現象が起きると辛くなります。
なお、研究では学術的に貢献できているかという視点が重要ですが、箱の隅をつつくような研究テーマと感じてしまうとモチベーションが下がってしまうこともあります。その研究が仕事に役立つ可能性を無理やりにでも連想するのも良いかもしれないです。
fujimiyu:周りも大学の非常勤講師として働きながら研究している人が多かったです。それでも、「研究だけに没頭したい」と思うこともあったので、可能であれば1年くらい研究に専念する時期をつくるのも精神的に良さそうです。
実はこの3年間の記憶がほとんどないほど忙しく、移動中も授業のレポートを採点したり研究のために論文を読んだりと常に何かをしていました。学費と生活費を稼ぐために仕事を多く入れていた時期もあり、その時は研究が進められずにストレスに感じていました。ただ、この忙しさを辛いとか苦しいと思ったことはなく、楽しんでいた記憶はあります。ストレス発散の時間も意識的に確保するようにはしていて、水曜日の夜は社交ダンスに通ってお好み焼き屋で晩ご飯を食べるという息抜きもしていました。
もう一度受験前に戻れるとしたら、どんな準備をしておく?
keiny:指導教官との相性は大事で、自分の興味を明確にしたり、研究の方向性を考えたりしておくと良いでしょう。研究会や公聴会に参加してみたり、学会発表でコミュニティを覗いてみたりするのもおすすめです。私の場合は共同研究で関わりのあった研究室の博士課程に進学しました。そのため、指導教官とも顔見知りで、研究内容も把握できていました。
また、一人で進めると研究がこじんまりとしてしまうので、共同研究者を見つけておくとネットワークを広げられたかもしれません。ただ、共同研究者が必須というわけではないので、「博士号取得に挑戦したい」という意志の方が重要です。
fujimiyu:事前に指導教官とのコミュニケーションを密にしておくことに尽きます。私の場合は、仕事で働いていた研究所の間接的な上長が指導教官でもあるという特殊なケースではあったのですが。大学の先生方は研究に関する質問には面識がない人からでも喜んで答えてくれるので、突撃で連絡してみるのも有効です。気になる先生を見つけて「ゼミに参加したいです」と連絡をすると、参加させてもらえることもあります。特に外部から受験する場合は顔を覚えてもらっておくことで、合格しやすくもなるはずです。調査・研究のアルバイトを募集している場合もあるので、まずはアルバイトとして知り合いになるという手もあります。
博士号取得までは長くかかるので、指導教官との相性が良くないと、途中で辞めてしまうケースもあります。私の指導教官は「修士課程の研究は学生の研究だけど、博士課程の研究は指導教官との二人三脚」と言っていました。また、調査分析に必要な研究費を確保できるかも死活問題なので、奨学金に応募するのもおすすめです。
修士課程から博士課程に進学する場合は、博士課程から新たな研究テーマに変えるのは珍しく、修士課程の研究テーマを発展させることになります。そのため、修士課程の研究内容で学会発表や論文投稿をしておき、アピールできる研究成果を一つでもつくっておくのが良いでしょう。
これから受験する人たちへのメッセージ
keiny:「何のために博士号を取得するのか?」「なぜ自分がその研究をするのか?」を棚卸ししておくと、自分に合った指導教官や研究テーマが明確になりますし、辛い時期でも頑張れると思います。
fujimiyu:お金とコネの確保をしましょう。たとえば、指導教官やステークホルダーとなる先生に自分の存在を認知してもらえるように、まずはアルバイトなどでつながりをつくり、アルバイト中は締め切りよりも早めに仕事を終わらせるなどの工夫をする。そうすれば、「この科研費が出る研究にメンバーとして参加しないか?」と声がかかったりします。地道につながりをつくっておかないと、博士課程で研究を進めていくのは難しいかもしれません。
まとめ
博士号取得には指導教官とのつながりを事前につくっておくことが重要であるという話が印象的でした。その点で言えば、本プログラムの運営をしているR4Dが様々な大学と共同研究をしているので、希望する研究テーマに合う指導教官を見つけやすい環境かもしれません。
また、keinyさんからは「私は前職で博士号を取得しましたが、研究テーマ不問で学費全額補助など様々なサポートを受けられる制度は珍しいので、ぜひ活用してほしい」というコメントがありました。本制度は、ありがたいことに何度も取材をしていただいてまして社外からも注目してもらっていますが、社会人博士を経験されたお二人の視点からも本制度の魅力を再確認できました。
第5期となる今回はどんな研究提案がくるのか楽しみです。ぜひまた続報を楽しみにお待ちください。