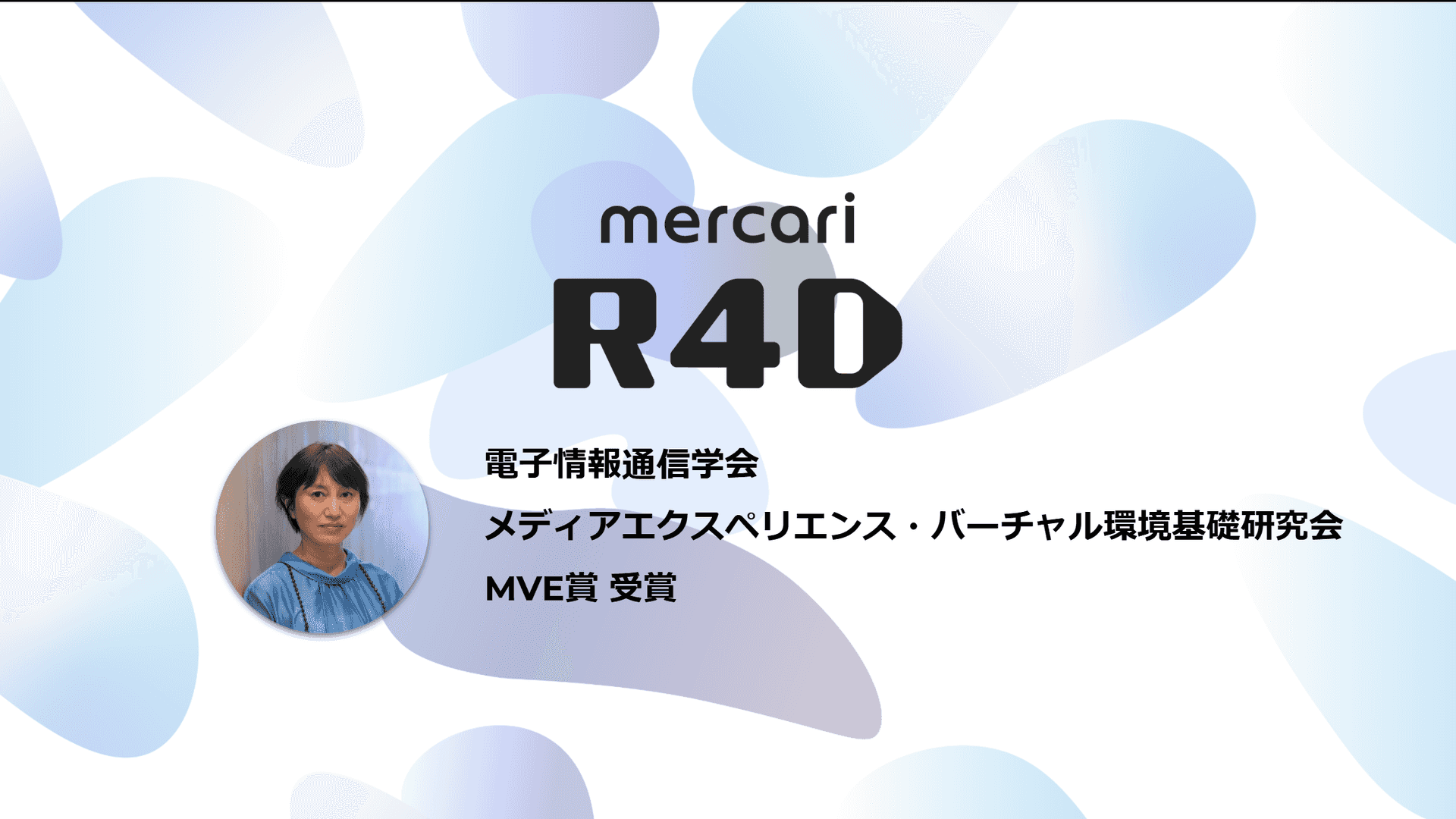mercari R4Dリサーチャー・藤原未雪が、「電子情報通信学会メディアエクスペリエンス・バーチャル環境基礎研究会」においてMVE賞を受賞いたしました。受賞した研究は、メルカリ・東京大学の包括連携プロジェクト「価値交換工学」に所属するAri Hautasaari氏(東京大学 大学院情報学環・特任准教授)、中條麟太郎氏(東京大学 大学院学際情報学府・修士課程)との共同研究です。
- 受賞名
- 電子情報通信学会メディアエクスペリエンス・バーチャル環境基礎研究会 MVE賞
- 発表テーマ
- フリマアプリでの商品説明文の作成における人・AI 協働の基礎検討
- 受賞理由
- 本研究では、フリマアプリにおける出品者の負担軽減を目的に、大規模言語モデル(LLM)を活用した商品説明文作成支援を検討しています。42名の参加者によるオンライン実験により、LLMの導入が出品者の体験や説明文の品質評価、商品の価値に与える影響を分析しています。実験の結果として、LLMを活用する支援により出品者の負担軽減の効果があることを確認するだけでなく、社会的手抜きや内容の正確性低下のリスクといった課題への対応を含むデザイン上の示唆についての考察が得られており、今後のさらなる発展を期待してMVE賞に推薦いたします。
- 論文PDF
- 開催プログラム
電子情報通信学会とは
電子情報通信学会は、電子情報通信技術の専門分野を幅広くカバーする我が国有数の規模を誇る学会です。メディアエクスペリエンス・バーチャル環境基礎研究会は、その中のヒューマンコミュニケーショングループに属する研究会として、メディアを利用した新体験の創出や新発見、VRをはじめとする今そこにない環境によるHI基盤に関連する研究成果の発表・議論の場を提供しています。
- 公式サイト: https://www.ieice.org/~mve/
受賞者からのコメント
藤原 未雪(mercari R4D, Researcher)
人間とAIの協働執筆が私たちの生活の中に入り込んできた今だからこそ、フリマアプリで出品者がAIを使って商品説明文を書いた場合、どのようなことが起こるかを明らかにしたいと考えました。苦心したのは実験デザインです。現在進行形の技術であるLLMを使って実験サイト上のフリマアプリでリアルな出品体験を再現することと、学術的な妥当性を両立させるためにどのようなデザインにしたらよいか、共同研究者であるAri Hautasaari先生と中條麟太郎さんと議論を重ねました。最終的に、出品者はLLM生成の魅力的な商品説明文により価格を再調整することや「社会的手抜き」が促進されるといった興味深い知見が得られました。今後は実験をより精緻にして、CtoC市場全体に及ぼす影響まで明らかにしていく予定です。2023年に続き、このチームで受賞できたことに感謝します。ありがとうございました。
Ari Hautasaari氏(東京大学 大学院情報学環 / インクルーシブ工学連携研究機構「価値交換工学」特任准教授)・中條 麟太郎氏(東京大学 大学院学際情報学府 修士課程 / インクルーシブ工学連携研究機構「価値交換工学」RA)
藤原未雪さんとの共同研究がMVE賞を受賞したことを、大変嬉しく思います。本研究では、生成AIの技術が一般的になり、文章執筆でも活用されつつある現代において、文章執筆の体験はどのように変化するのか、商取引にはどのような影響が生じるのかを探求しました。これは、少し先の未来におけるUX(ユーザ・エスクペリエンス)の可能性を、学術的に明らかにしようとした研究であるとも言えます。私たちは、「望ましいコミュケーションとは何か」という共通の問いを持ちながら、言語学、情報学、心理学の間で、社会実装と研究の間で、現在と未来の間で、メルカリと東京大学の間で、様々な視点から議論を進めてきました。これからも、新しいテクノロジーと、少し先の未来のコミュニケーションの可能性に着目して、研究と社会実装の両輪で活動していきます。
※価値交換工学の関連ページ:https://r4d.mercari.com/vxe/