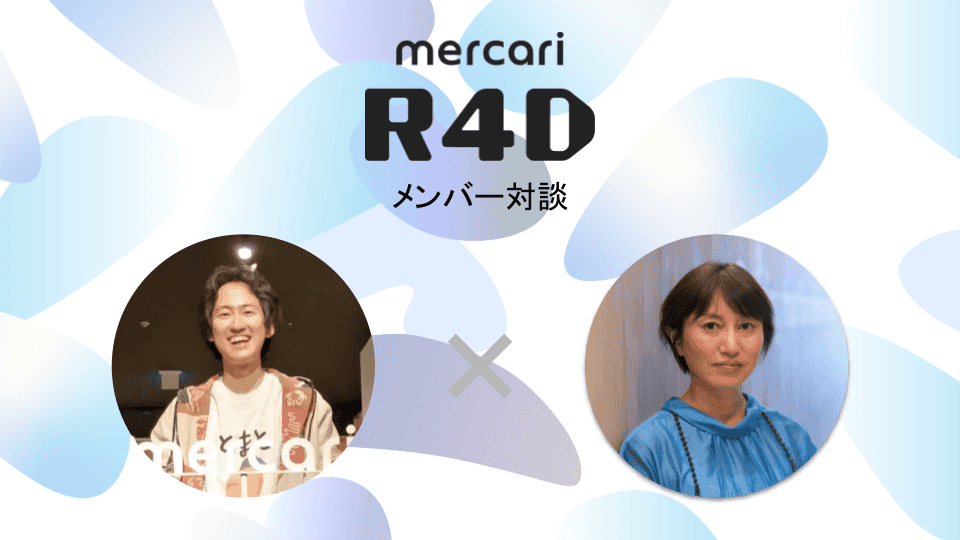こんにちは。mercari R4DのResearch Acceleration Teamの藤本翔一(@sho-1)です。私は2020年4月に、Research Administrator(研究コーディネーター)としてR4Dにジョインし、たくさんの研究者や実務者のメンバーとをつないだり、研究開発を進めるためのあらゆる伴走の仕事をしてきました。前回の記事(Part.1)では、私の視点から「研究をつなぐひと」としての活動を概観しました。
前回記事:「研究をつなぐひと」(Part.1 概観編)〜ひとの好奇心に巻き込まれ巻き込みながら、みんなの好奇心を拡げ重ねていく仕事〜
今回は、「研究をつなぐひと」の役割についてより深く振り返るために、長く一緒に働いてきたR4D Researcherの@fujimiyuさん(藤原未雪)をお誘いしてみました。私はfujimiyuさんの好奇心やモチベーションに巻き込まれながら、私もfujimiyuさんをメルカリのさまざまな課題や議論に巻き込んでいき、そうやって好奇心とプロジェクトの輪を拡げながら研究をコーディネートしてきました。今日は、fujimiyuさんのリサーチャーの視点から、「研究をつなぐひと」の動きや価値について掘り下げてみたいです。
社内イベント リアルフリマにて
左@sho-1, 中央@fujimiyu, 右@inomari
fujimiyuさんのご紹介
sho-1:fujimiyuさん、今日はありがとうございます。一緒に過去の仕事を振り返ることをとても楽しみにしていました。早速ですが、fujimiyuさんの自己紹介をお願いします。
fujimiyu:私は文章理解と日本語教育を専門に、さまざまなコミュニケーションに関する研究に取り組んでいます。もともとメルカリアプリのファンで、2020年にメルカリアプリ上の研究テーマ案をもってR4Dにお問い合わせをして、最初は客員研究員として、それから2022年6月からはリサーチャーとしてR4Dにジョインしています。
sho-1:ありがとうございます。一番最初のfujimiyuさんの研究テーマからよく覚えていて、この研究はとても面白いし、メルカリにとってとても重要だと思って、ご一緒できることがすごく嬉しかったです! それでは、順に振り返っていきましょう。
「客員研究員」としての最初のプロジェクト
fujimiyu:最初、R4Dにお問い合わせをしたところ、お返事をいただけて、まずは@misatoさん(退職済み)や@tagoさんたちと、研究テーマを絞らずに会話を進めていました。コラボレーションの前に研究テーマを決めておくことが一般的であることを思えば、R4Dの研究への向き合い方は新鮮でした。MTGごとの具体的な資料を準備しようと思ったら、「そういう資料は今はまだなくても大丈夫ですよ」と言われたのが印象的でした。その流れの中で、プロジェクトが決まる前に「客員研究員」としてR4Dと関わることが決まりました。
sho-1:その頃、私は、当時のマネージャーだった@tagoさんたちから、fujimiyuさんのコーディネートをアサインされ、fujimiyuさんとお話させていただくようになりました。 そういえば、fujimiyuさんの肩書を「客員研究員」と命名したのは私でした。当初は「業務委託リサーチャー」という名称だったのですが、もっと研究所らしいかっこいい名前をあれこれ考えたのでした。
fujimiyu:そうした配慮もR4Dに馴染むうえで助かりました。
sho-1:そして、Language Education Team(LET)、Analytics、Brandingなどさまざまな社内のチームメンバーとのディスカッション機会を私がセッティングしたりしながら、議論を経て、日本語非母語話者の留学生のフリマアプリ上での困難点の調査プロジェクトを進めることになったのでした。
fujimiyu:2020年11月にR4Dで客員研究員として働くこと正式を決め、プロジェクトが始まったのですが、同時期に2021年3月からは大学の講師としてウズベキスタンに移住することも決まっていました。ですから、短い期間で一定の成果や区切りも必要となり、不安もありました。
そのようななか、sho-1さんが入ってくれてからは、研究テーマ設計、進捗管理、関連部署とのディスカッション、ユーザー同意書の作成や研究開発倫理審査への付議など、プロジェクトが具体的に前進するようになりました。毎回のMTGで次のMTGまでのNext Actionも明確になり、私もそれまでに絶対にその分析を進めなくてはならない状況ができて、どんどん進めることができました。2021年3月9日に社内向け勉強会で結果報告を行い、3月17日に出国するという怒涛のスケジュールでした。
社内向け勉強会は、イベントのオーガナイズ、当日のファシリテーション、事前の資料の論点整理の壁打ちもsho-1さんがしてくださいました。
もしもこのプロジェクトの研究テーマ設定が間に合わなかったり、形にならないまま出国することになっていたら、ウズベキスタンでの仕事の方に専念するようになってR4Dとのご縁が途絶えてしまうなんてこともあったかもしれません。タイトなスケジュールの中でも一定の成果を残せたことで、R4Dで研究を進める自信になりましたし、sho-1さんと一緒に進めていく中で「R4Dで研究を続けられたら楽しいだろうな」と感じられ、現在につながっています。
ウズベキスタン時代からR4D入社へ
sho-1:「R4Dで研究がしたい」と思っていただけてとても嬉しかったです。出国前のプロジェクトで勢いが付いて、ウズベキスタン移住後も、R4Dの客員研究員としてご一緒できましたね。
他にも、東京大学RIISEとR4Dで「価値交換工学シンポジウム」というオンラインのシンポジウムを企画した際にもご協力いただき、コミュニケーション研究をテーマにした、Hautasaari Ari先生との対談動画を作成したこともありました。
sho-1が企画・ファシリテートを行ったfujimiyuさんとAri先生の対談動画コンテンツ
fujimiyu:移住してすぐということもあって、慌ただしい中での撮影だったのを覚えています。動画撮影とスクリプト確認のスケジュール自体もタイトだったり、対談当日は動画撮影がウズベキスタン時間の午前6時に始まるということで、4時半に起きて準備をしたこともありました笑
sho-1:そんなに朝早かったんですね! ご協力をありがとうございました。動画は社内外で多くのひとに観てもらえたと思います。
fujimiyu:当時はまだ「R4Dって何の部署なの?」と聞かれることも多かったですが、最近はR4Dを知ってもらえていることも増えてきましたね。こうしたPR活動も大事ですね。
sho-1:こうした企画にもご協力いただきながらも、R4Dで研究を一緒に進めましたね。
fujimiyu:そうですね。ウズベキスタンで働き始めた頃はR4Dでの次の研究テーマを模索していました。そのヒントもsho-1さんからいただいたのでした。sho-1さんからVOC(Voice of Custumer)新聞という、お客さまの声がまとまっている資料をシェアしてもらったり、お客さま向けのメッセージ文案に関する社内の議論を紹介してもらったり、CS(カスタマーサービス)のメンバーとのカジュアルミーティングをセッティングしてもらったりしました。それらの機会からヒントを得ながら、お客さま同士のコミュニケーションに関する研究やCSからのメッセージに関する研究について考えました。
sho-1:当時、VOC新聞はR4Dの研究テーマ検討のためのヒントの宝庫で、必要な手続きを取ったうえで、多くの研究者にシェアするようにしていました。私はそうやって、研究者が情報や人にアクセスできる機会を創っていくことが、コーディネーターとしての大事な仕事の一つだったと思います。
その後の展開を伺えますか。
fujimiyu:2022年5月にウズベキスタンから帰国して、2022年6月にR4Dにジョインしました。帰国してからは価値交換工学のミーティングやAri先生のゼミにも参加するようになりました。こうした機会にAri先生と話しているうちに意気投合し、共同研究を始めることになりました。この成果が「HCGシンポジウム2023」で最優秀インタラクティブ発表賞を受賞し、その後も複数の学会での受賞に繋がりました。
sho-1さんはもともと、私の研究とは別にAri先生のコーディネートもされていたり、Ari先生との対談動画の機会もあったり、ここに至るまでのさまざまなこ゚縁を感じています。
- 参考:R4Dリサーチャー・藤原が電子情報通信学会「HCGシンポジウム2023」において最優秀インタラクティブ発表賞を受賞
- 参考:R4Dリサーチャー・藤原と東京大学(価値交換工学)のAri Hautasaari氏と中條麟太郎氏との共同研究の成果が「電子情報通信学会メディアエクスペリエンス・バーチャル環境基礎研究会」においてMVE賞を受賞
- 参考:R4Dリサーチャー・藤原と東京大学(価値交換工学)のAri Hautasaari氏と中條麟太郎氏との共同研究の成果が「INTERACTION 2025」においてインタラクティブ発表賞を受賞
「研究をつなぐひと」がもたらすセレンディピティ
sho-1:fujimiyuさんのR4Dでのご活躍を通して、「研究をつなぐひと」としての私の活動も振り返ってきました。私が意識していたのは、fujimiyuさんの好奇心とメルカリのさまざまな課題や議論の重なるポイントを見つけ、拡げていくことだったのですが、fujimiyuさんのリサーチャーとしての立場からはどのように映っていましたか?
fujimiyu:今回の対談を通じて、セレンディピティという言葉が浮かんできました。でも、sho-1さんの立場からすると、「意図しながらつくる偶発性」という側面もあるのでしょうね。さまざまな局面で、研究者や実務者をつなぐために尽力してくれているのだろうと思いました。
sho-1:私は自分で自分のことを「研究のお見合い屋さん」と呼んでいます。研究者と実務者が上手くマッチングするような機会もあれば、そうはならない機会もあります。たしかに、セレンディピティを狙って種を撒くような役割なのかもしれません。また、後になってから、思ってもいなかったようなこ゚縁に発展していたことを知るような機会も体験できました。
fujimiyu:「ヒントは現場の外にある。答えは現場の中にある」という私の好きな言葉があります。「自分の研究をどのように進めるべきか?」「どこで誰とどうやって研究を進めるべきか?」など、研究者本人には意外と見えないものです。そんな時に、sho-1さんのような人が、研究者の好奇心とメルカリの課題や議論のマッチングを促してくれたり、そうやってさまざまな人や機会をつないでくれると、研究者として大変助かります。そのようなコーディネートをするためには、各分野を幅広く理解する学際性も必要だと思います。思いもよらない領域の掛け合わせを思いつくためにも重要ですね。
sho-1:前回の記事でも振り返りましたが、「研究をつなぐひと」の仕事に、私が学生時代に文系理系幅広い分野を学ぶコースにいたことが役立っているなと思います。
まとめ(編集後記)
sho-1:今回はfujimiyuさんとの仕事を振り返りながら、「研究をつなぐひと」についてリサーチャー視点からお話しいただきました。「意図しながらつくる偶発性」や「ヒントは現場の外にある、答えは現場の中にある」というキーフレーズも得られ、学びが多い時間になりました。もう5年も前のことだなんて、とても懐かしいですね。ありがとうございました!
fujimiyu:私もR4Dでの研究活動を振り返る機会になって、とても懐かしく、とても楽しかったです。ありがとうございました!